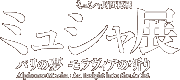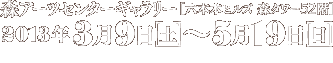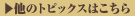1910年、パリ時代から温めていた《スラヴ叙事詩》の構想を実現するために、ミュシャは長年離れていた祖国へ戻ります。アメリカで資金援助を得た後、西ボヘミア地方のズビロフ城をスタジオとして借りたミュシャは、余生の殆どをこのプロジェクトに費やします。《スラヴ叙事詩》でチェコ人とスラヴの同胞たちの、共通の栄光と悲哀の歴史を描くことにより、長年の植民地政策によって離散していた民族の統一を促し、各国家の独立への原動力にしようとしたのです。ミュシャのチェコ独立への悲願は、第一次大戦の終結とともに成就し、1928年、チェコスロヴァキア独立10周年にあわせて完成した《スラヴ叙事詩》はプラハ市に寄贈されます。《究極のスラヴ民族》には「人類のためのスラヴ民族」という副題がつけられており、スラヴ民族は一致団結しながら他民族との共存に努め、究極的には人類の平和に貢献するべきである、というミュシャの思想がうかがえます。
このセクションでは、《スラヴ叙事詩》を軸に、プラハ市民会館の壁画の習作、祖国愛をテーマにした油彩やポスター、さらに、ミュシャ最後のプロジェクトである三部作 (未完)、《理性の時代》《叡智の時代》《愛の時代》などを展示します。これらの作品を通して、パリ時代に確立されたミュシャ様式が、彼の思想伝達の手段としてどのように変遷していったのかを考察します。
![]()
章解説:佐藤智子(ミュシャ財団キュレーター)
作品解説:千足伸行