| 第1469回 2019.03.31 |
ガラパゴス諸島 の科学[特別編] | 場所・建物 地上の動物 水中の動物 |
昨年、桝アナと佐藤アナが取材した「生き物たちの楽園」ガラパゴス諸島。ガラパゴスに行くのが生涯の夢だったという桝アナが、貴重な生き物たちを目の前に大興奮!数多くの貴重な映像を撮影することができました。
今回は、放送時間の都合上で放送できなかった未公開シーンも含めた、奇跡の島・ガラパゴス諸島の科学特別編をお届けします。
ガラパゴス上陸!自然を守る仕組み
成田空港を出発。およそ13時間かけてアメリカへ。さらに、エクアドルの首都キトまで5時間。キトで一泊したのち、さらに3時間半かけてガラパゴス諸島へ。乗り継ぎも含めると30時間以上の長旅です。しかし、ガラパゴス諸島ならではの光景に桝さん、到着した途端に大興奮!自他共に認める変なテンションになっちゃっています。飛行機を降りてすぐ、足元には外から植物の種などを入れないための消毒マットがあり、その上を歩かなくてはなりません。

さらに、カバンの中身も検査。生の果物や、生き物を持ち込んでいないか、徹底的に調べられます。しかも、キトからガラパゴスへ向かう飛行機の中では、手荷物に殺虫剤をかけて消毒するという徹底ぶり。そして、ガラパゴスの空港では、島の環境を守るためにソーラーパネルや風力発電などの再生可能エネルギーだけを使っています。
空港を出ると、いきなり“ダーウィンフィンチ”に遭遇!ガラパゴス諸島にしかいない、とっても貴重な鳥です。子供の頃から図鑑で見て憧れたというダーウィンフィンチに桝アナの興奮が止まりません。
空港を出るバスに乗り、今度は船。港ではカニやペリカンなど、次々と珍しい動物たちが現れます。船からは、鳥たちが獲物を捕まえに海へダイブする姿が。「ガラパゴスは動物が人間を気にしてないから透明人間になった気分だ」と桝アナ。そう、ガラパゴスの特徴は、生き物たちの警戒心の弱さ。

例えば、研究者にインタビュー中もガラパゴスにしかいない、超貴重な鳥がいきなり頭にとまったり、街を歩いていても野生のアシカが授乳していたり、警戒心がまるで感じられません。
どうしてこんなに警戒心が弱いのでしょうか?一説には、天敵になる大型の肉食動物がいないからだと言われています。ガラパゴス諸島は海底火山の噴火によってできた海洋島。大陸とつながったことがないのでもともと生き物がいません。運良く島にたどり着いた生き物だけが、天敵のいない環境で暮らすうちに警戒心が弱くなったと考えられているのです。
ガラパゴス独自の進化!ゾウガメ&イグアナ
ガラパゴスだからこそ撮れた迫力の生き物たちの映像を紹介。まずは、ガラパゴスを代表する生き物、ガラパゴスゾウガメ。ゾウガメを探したのは、サンタ・クルス島。森の中を探すことわずか1分。世界中でここだけにしか生息していないガラパゴスゾウガメを発見!ガラパゴス諸島にはおよそ2万頭が生息。

これほどの数の野生のゾウガメを見られる場所は、世界でもほとんどありません。車が通る道路を我が物顔で歩く姿まで見られます。陸に住む泳げないカメの中では世界最大。大きいものでは体長1m50cmで、体重300kgに達するものもいます。ここでの桝アナ一押しの貴重映像は、「ガラパゴスゾウガメの音」。「バリバリバリ」と、草を豪快に引きちぎる姿は、まるで恐竜。

さらに、カメラマンが移動しようとした、その時!足音に驚いたのか、首を甲羅の中に引っ込めると同時に息を吐き出し、「シュー」という威嚇の音を出したのです。野生のゾウガメにここまで近づけるガラパゴスだからこそ聞ける音でした。
そして、ガラパゴスゾウガメにはさらなる秘密が。実は、住む島によって違う形に進化しているというのです。そのゾウガメに会うため、ガラパゴス最南端の島、エスパニョーラ島へ!普段は観光客の立ち入りが制限されている島ですが、特別な許可を得て、ゾウガメの研究者とともに島の内陸部へ。道なき道を2時間歩き、ついにそのゾウガメに会うことができました。エスパニョーラ島で進化したゾウガメは、サンタ・クルス島のゾウガメと違い、キリンのように首が高く伸びています。

サンタ・クルス島のゾウガメは地面に豊富に生える草を食べますが、一方、あまり草の生えないエスパニョーラ島に住むゾウガメは、高いところにある木の枝やサボテンを食べなければなりませんでした。すると、長い年月をかけて進化し、甲羅の形が変化。

首を高く上げられるゾウガメだけが、生き残ったのです。ガラパゴスのゾウガメたちは島によって、それぞれの環境に合わせて甲羅の形が変化したと考えられているんです。
さらに、ガラパゴス諸島には普通では考えられないような進化をした生き物がいます。それは、ガラパゴスウミイグアナ。イグアナといえば、普通は陸で暮らす爬虫類ですが、ガラパゴスウミイグアナは、世界中のイグアナで唯一海に潜り、岩に鋭い爪でつかまって海藻を食べるイグアナです。ガラパゴスにも、陸で暮らすイグアナがいますが、彼らは食料になるサボテンの実が落ちてくるのを、その下でずーっと待つ、という生活をしています。実が落ちると仲間同士で奪い合うことがあるほど厳しい環境です。一方、ウミイグアナが暮らすガラパゴス周辺の海は栄養豊富なため、生き物の宝庫。彼らの食料になる海藻もたくさん生えています。リクイグアナが1万匹ほどしかいないのに対して、ウミイグアナはなんと20~30万匹。

海に適応し、繁栄することができたんです。とはいえ、海で生きるのも楽ではありません。外の温度で体温が変わってしまう変温動物なので、太陽の光を浴びて体温が上がってからでないと、冷たい海には入れないんです。体温が上がると海へ。しっぽを上手に使って泳ぎます。しかし、4つの海流が集まるガラパゴス周辺の海は、流れが強烈。激しい流れの中で潜って岩にしがみつき、息を止めていられる10分ほどの間に海藻を食べます。カメラマンが体勢を崩すほどの水流でも、ウミイグアナびくともせず、鋭い爪で岩に張り付いています。しかし、時には冷たい海に体温を奪われ、体が動かなくなり溺れ死ぬこともあるそうです。ウミイグアナは海で豊富な食料を手に入れた代わりに、常に命がけのダイビングをしていたんです。
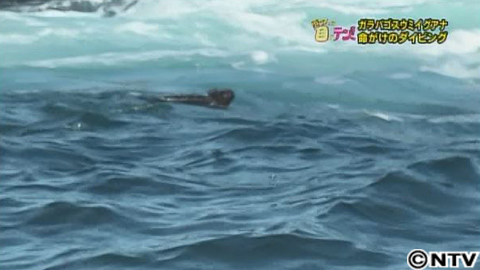
ガラパゴスに生きる鳥たちの求愛ダンス!
続いて紹介するのは、ガラパゴスに生きる貴重な鳥たち!中でも求愛ダンスが見事な3種類の鳥に注目。
まずは、ガラパゴスを代表する鳥、グンカンドリです。翼を広げると2mもの大きさで、他の海鳥の餌を奪うことがあるので、軍艦鳥という名がつきました。求愛に使うのは、喉の赤い部分。風船状になっていて、ここに空気を入れていくんです。この自慢の喉袋を使った求愛ダンスが・・・喉袋を広げて「カタカタ」と鳴らす行為。

喉袋は、鮮やかで大きな程メスにモテます。上空を飛ぶメスに、必死にアピール!メスが来てくれればすぐにカップル成立、と思いきや、そうではありません。グンカンドリは2~3年に一度しか卵を産まないため、メスのオス選びはとてもシビア。せっかくメスがやってきても、気に入らなければ飛び去ってしまいます。半日、撮影を続けましたが、交尾までいたったオスを見つけることはできませんでした。
続いては、青い足が特徴のアオアシカツオドリ。そのきれいな足をモチーフにしたアクセサリーが、お土産として大人気。ガラパゴスを代表する鳥の一つです。普段はとぼけた表情をしていますが、狩りのときには豹変。海の浅いところを泳ぐ小魚を食べるアオアシカツオドリ。時速50キロものスピードで海に飛び込み、小魚をハントします。数百匹が一度に狩りをする姿は、圧巻。
そんな彼らの求愛ダンスは・・・青い足を見せつけるように足踏み。

青ければ青いほど健康だそうで、メスにモテます。メスも同じように踊ってくれればカップルが成立します。しかし、観察していたペアは、なんと途中でメスが興味を失い寝始めてしまいました。くちばしで突っついてみても、全く反応なし。残念、カップル成立ならず…。
見事、カップルが成立すると雛が生まれます。しかし、彼らの子育てもとても大変です。アオアシカツオドリは、2~3個の卵を産みますが、餌の少ない年は1匹しか生き残れません。餌を取り合って、体の大きいヒナが小さいヒナを殺してしまうこともあるのだとか。自然界のシビアさを象徴する光景が広がります。
最後に紹介する求愛ダンスは、ガラパゴスアホウドリ。彼らが暮らすのは、ガラパゴスの最南端、エスパニョーラ島。今回は、国立公園の調査に同行するという形で、特別に撮影が許可されました。羽を広げると3メートルもあるガラパゴスアホウドリ。彼らが子育てをするのは、世界でもここエスパニョーラ島だけ。ガラパゴスアホウドリは、夫婦交代で子育てをします。餌を取りに行かないほうが必ずヒナの世話をするのです。しかも、40年ほどの寿命の間、生涯同じペアで連れ添い、何度も子育てをします。そのため、彼らの求愛ダンスは、新しい相手を見つけるためだけではなく、夫婦の大事なコミュニケーションでもあるのです。
長年連れ添った夫婦の一糸乱れぬ求愛ダンスは・・・じっと見つめ合い、激しくくちばしを打ち付ける!彼らはこうやって、互いの絆をより強めていると考えられています。

