| 第1639回 2022.08.21 |
かがくの里 の科学 | 場所・建物 地上の動物 物・その他 |
人と自然が豊かに共存する里山づくりを目指し続ける長期実験企画、かがくの里!今年、里の粘土質の土に目をつけ、木材利用の専門家村田先生が、里の粘土で陶芸に挑戦しようと考えたんです。そもそも、日本各地に数多くある陶器の産地はその土地に、焼き物に適した土があることから、陶芸の里として発展しました。その際、周りの木で薪や炭を作り、陶器を焼いてきたんです。そこで、かがくの里でも里の粘土で器を作り、裏山の間伐材の炭で焼くという、里山再生陶芸プロジェクトをスタート!
さらに今回、もう一つ新プロジェクトが始動!それは、夏の夜を幻想的に彩る、あの昆虫を呼ぶ新企画!今回は、かがくの里 2つの新プロジェクトが始動スペシャルです!
新プロジェクト!ホタルを里に定着させよう
一般に、里山の水田や水路など、人手が加わった栄養分が豊富な環境周辺に生息するホタル。かつてはどこでも見られる身近な虫でしたが、水質汚染や都市化による人工照明といった光害など環境の悪化によって、近年、生息地は大幅に減少、ホタルの数も減っているんです。
定期的な昆虫調査で、貴重な虫が多く見つかっているかがくの里は、整備が進みどんどん昆虫にとって暮らしやすい環境になっています。そんな里の生き物達を撮影し、一冊の図鑑にまとめた「里山の生き物図鑑」も大ヒット中ですが、まだホタルは載せられていません!
そこで、里にホタルを自然に定着させることを目指した“かがくの里をホタルの里に!プロジェクト“がスタート!
実は、ホタルが増える上で必要なのが、カワニナという巻貝。流れが緩やかな河川や、ため池の泥底などに生息する貝。エサとなるカワニナがいないと、ホタルの幼虫は成長できません。
かがくの里の近くの川にいるのか?と思ったら、なんとすぐにカワニナを発見!カワニナは炭酸カルシウムが殻の主成分。

そのため、水分中にカルシウムイオンなどが不足していると、殻が薄くなり欠けやすくなることがあるそう。また、川の水の酸性度が高いと溶けてしまう場合も。カワニナを発見できたということは、この川付近にホタルがいる可能性があるということ。
ということで、繁殖シーズンで活発に飛び回る6月の夜、ホタルの捜索を行いました!今回狙うのは、ヘイケボタルとゲンジボタル。
ヘイケボタルは日本全国と朝鮮半島、中国の北部などに分布し、ゲンジボタルは日本の固有種。よく耳にするこの2種類、夏の夜に光りながら舞う姿が印象的ですが実は光り方が違うんだそうです。ヘイケボタルは1秒に1~2回点滅するように光り、ゲンジボタルは2~4秒に1回長い周期で光るのが特徴なんです。
さっそく、前回の調査でカワニナがいた小川付近を捜索。と、ライトを消した瞬間のことでした!暗闇に光る物体を発見!間違いなくホタルです!
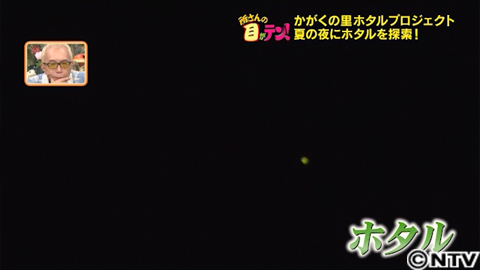
点滅が早いことからヘイケボタルのよう。さらに!別の場所を探索してみると、葉っぱに止まるホタルを発見。先ほどのように光りながら飛び回っているのはほとんどがオス。メスは、草や木の葉に止まっていることが多いといいます。
すると、葉っぱに止まっていた1匹のもとへ、もう1匹やってきました!ホタルは暗闇の中、光でコミュニケーションを取り、交尾する相手を見つけると、オスがメスの場所で移動します。木の葉に止まっているメスのところにオスが近づいていると思われるので、もしかするとカップルが成立した可能性が!
今度は、光る周期が違うゲンジボタルを捜索。すると、法師人さんが高く飛ぶホタルを発見。かすかではありますが、ゲンジホタルと思われる光をとらえることができました。
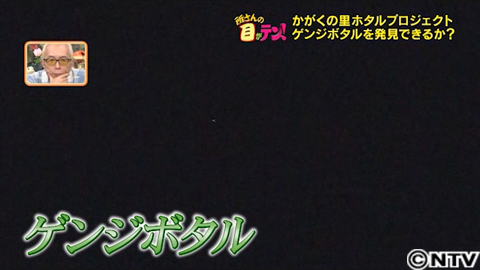
ちなみに、ゲンジボタル、関東と関西で光る周期が違うといいます。関西では2秒に1回。関東は4秒に1回。そんなゲンジボタルですが、今問題が起きてるそう。関西のゲンジボタルを関東や東北で放すことで、関西型のホタルが関東で広がっているといいます。この交雑によって純粋な東日本型が姿を消す可能性があるというんです。
今回ヘイケボタルとゲンジボタル、どちらの存在も確認できましたが、今後は、自然にその数が増えてくれるように、まずは水辺の環境をより良く整えていく必要があります!

里山再生陶芸プロジェクト始動!
陶芸には欠かせない粘土。そもそも粘土とは、岩石が風化、堆積することでできる非常に粒子が細かい土のこと。岩石が雨風にさらされたり、微生物の作用をうけながら長い年月を経ることで、砕け、細かい粒子となり、少しずつ地表に堆積していったものが粘土なんです。
細かい粒子同士は、焼くことで互いに結合して固まるので、器になります。さらに、粘土は水分を含むとねっとりとしたものになるのが特徴。かがくの里の土壌も、元々は、粘土質の土でした。粘土質の里の土は、陶芸に適しているかもしれない!ということでまずは、粘土探しから。
2人が狙ったのは、排水工事のため掘った穴。すると、自ら花瓶も焼いている里の達人、西野さんから土選びのポイントが!なんと、作物を育てている表面の土は陶芸に向かないそう。ということで、それぞれ「ここぞ」という場所の土を採取。
里の粘土質の土は、陶芸に向いているのか?

そこで村田先生の知り合いで北海道在住の陶芸家に里の土を調べてもらうため旭川の山奥に向かいました。
お会いしたのが、陶芸家の工藤和彦さん。里山で、土地の土や木を使い、器を作っていた昔と同じく、身の回りのもので作品を作りたい。そんな思いから、北海道の裏山で工房を開いた工藤さん。まさに、今回のプロジェクトの先生にピッタリです。
ということでさっそく、工藤さんの使っている土を見せていただきました。

すると、硬くてコチコチのものが、砕いてすりつぶすと、粒子が細かく一定でサラサラに!そこに水を加えて、工藤さんに練ってもらうと、陶芸でよく見る“粘土”に!

工藤さんが地元で見つけた粘土は、中国やモンゴルから飛んできた黄砂が堆積したもの。風に巻き上げられた黄砂の中でも、北海道まで届くものはとても細かく、これが陶芸用に向いた粘土にだったと考えられます。
そして、ここからが本題!かがくの里の土は粘土として使えるのでしょうか?
ということで、中でも一番よさそうな土を工藤さんに選んでもらい、水で練った後、テストピースといわれる石膏の型で、型取ります。これを、電気釜に入れ、土を焼き固めるのに必要な1180℃以上の高温で、1日焼くんです。
もし向かない土の場合、溶けてしまうそう。
翌日、焼いた土の状態を確認です。すると、焼く前と同じ形のままです!里の土が、陶芸に必要な高温に耐えられるとわかりました!

