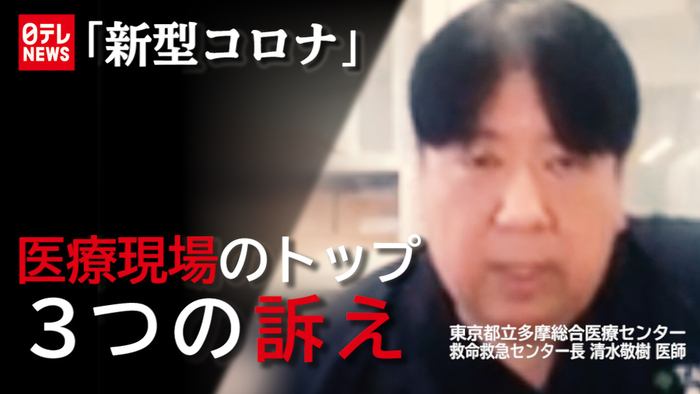
感染しても約80%は軽症で済むとされている、新型コロナウイルス。
しかし、5%程度は重篤化し、亡くなる方もいます。
いま医療の最前線では何が起こっているのか?
人工呼吸管理を含めた、重症患者を治療している医師・清水敬樹(しみず・けいき)氏に現状の対応や課題、今後の要望を聞きました。
(目次)
1)未曾有の災害、最悪の場合「命の線引き」も
2)医療従事者を守らなければ、医療行為はあり得ない
3)「現場判断」ではなく「行政判断」を
1)未曾有の災害、最悪の場合「命の線引き」も
--これまでに、どのくらいの「新型コロナ」重症患者を治療?
人工呼吸管理を含めた重症患者を7人程度、治療させていただいています。

テレビ電話に応じてくれた清水医師
--現場では、どのような対応を?
我々の施設(東京都立多摩総合医療センター)において、院内の一般病棟レベルでは呼吸器内科が軽症患者を診ているため、救命救急センターとしては重症患者のみを対応しています。
対応が始まったのは2月中旬くらいからです。
症状としては呼吸がよろしくなく、人工呼吸器を使っている状況で、臓器障害なども進行している流れで、さらに呼吸も悪化する。
そこで我々は体外式膜型人工肺(ECMO)も導入しています。
一旦、呼吸状況が悪化した場合には、もう短時間で坂道を転び落ちるように進む、そういう印象が強いです。
--具体的な悪化のスピードは?
例えば、症状が増悪して酸素投与を開始。
その後、どんどん短時間で気管挿管、人工呼吸管理、さらに人工肺という流れが、数時間から半日程度で移行せざるを得ない事例も確認されています。
やはり早め早めの対応は重要だと考えております。

医療現場の様子
--医療現場の体制は万全?
ひとつの医療機関で対応できる重症患者は、やはり2~3人が限界です。
というのも、「新型コロナ」重症患者の他にも、通常の重症患者の業務が当然あります。
その患者もないがしろにできませんので、その体制は維持しながら配置の変換を行っています。
「新型コロナ」患者に対しては、陰圧個室(=ウイルスが外部に流出しないよう気圧を低くしている病室)で、ある程度限定したスタッフで対応するというシステムになっています。
このような特別な環境下で安全を担保する意味でも2~3人が限界です。
--感染が拡大したら?
医療崩壊と言っていいと思います。
単純に計算上はベッドが足りなくなります。
我々の施設において重症患者を対応する陰圧個室は3床です。
重症患者を数名しか見られない、という実情があります。
感染拡大で重症患者も増えた場合、最悪のケースですが、命の線引きといいますか、年齢で対応を変える流れも出てくる可能性があると思います。
--有事の状態?
現状、未曾有の災害である、ということは間違いありません。
日本は様々な災害を乗り越えてきた実績もあるので、経験を盾にしながら考えるしかないと思います。

医療現場の様子
2)医療従事者を守らなければ、医療行為はあり得ない
--医療現場の状況は?
患者に対してしっかりとした対応をするのは当然です。
それに加えて医師や看護師・医療従事者の安全を120%以上担保することが大前提です。
そこへのこだわりをしっかり持っていかないと医療現場としては成立しないし、もたない。
--病院スタッフの感染を防がないといけない?
医療従事者だとしても、自宅に帰ったら父親でもあり、母親でもあり、あるいは息子、娘なんですね。
スタッフを守るのは最優先であるべきで、その担保なくしての医療行為はあり得ないと感じています。
一気に20~30名の重症患者をひとつの医療機関で診ろといわれても、それは間違いなく、医療従事者の感染へつながっていきます。
その点からも医療崩壊といわざるを得ません。

医療現場の様子
--医療現場で足りてないものは?
マスクは非常に足りていません。
いろんな使用方法に対して、制限しながらやりくりしている状況です。
身を守る大前提が崩壊する危険性が高いので、そこは最優先で行政に対応していただく必要がある。
院内感染が非常に危惧されます。
--現場の医療従事者たちは、どのような精神状態?
現場の最前線で頑張るスタッフたちは、医療従事者の使命とか誇りを持って頑張ってらっしゃるのが事実です。
一方で、恐怖心を持っているのも事実。
そのようなジレンマの中でやっているのが本当のところです。
スタッフたちのことを考えた上で、しっかりとしたケア、万全な体制、マスクが足りないとかは絶対に避けなければなりません。
3)「現場判断」ではなく「行政判断」を
--医療機関全体の体制は?
重症患者の受け入れに対してはですね、やはり医療機関によって温度差があるのが事実です。
それは当然、経営陣の経営判断などありますから。
ただ、本来は受け入れるのが使命。
そのことを非常に強く感じながら、現場の判断があります。
ジレンマの中で、みなさんやってらっしゃいます。
--行政の後押しが必要?
後押しされれば、受け入れ可能な医療機関が増えると思っています。
介入も含めて、お願いするような体制にもっていくことを、国含めて行政が考えているのかどうか。
その辺でアクションが変わっていくと思うんです。
ぜひ行政判断をしていただければと考えています。
ただ、施設の構造上の問題とかスタッフの教育の問題で、十分でないところで患者をみるリスクもあります。
明らかに感染症患者を診る力量が無い医療機関に、無理矢理に患者対応を強いることで、医療従事者の身を守る前提が弱まると、医療体制が崩れかかる。
繰り返しますが、重症患者の治療にあたる最前線のスタッフの安全を守る必要があります。
マスクや個人防護、そういう武器がない治療はあり得ませんので、配給はしっかりして欲しいです。

--最後に伝えたいことは?
そうは言っても、行政はもちろん、救命救急治療のスタッフ、公衆衛生の先生方、感染症科、呼吸器内科、各種専門家、各々が厚いネットワークを張って尽力されています。
各種医療機関、医療施設も全力で対応しているのは事実なので、行政も含め、機能的に患者の管理をしていければと思います。
■清水敬樹 医師

東京都立多摩総合医療センター・救命救急センター長。
1995年、広島大学医学部を卒業。
公立昭和病院にて救急医学の研究を積む。
専門は救命救急治療、集中治療、広範囲熱傷、頭部外傷、脳蘇生、胸部外傷、ECMO、熱中症、母体救命。
現在は、東京都立多摩総合医療センター救命救急センターで救命対応および院内重症患者の集学的治療を行っている。
【関連記事】
「新型コロナ」いま知るべき5つのこと 感染者を治療した医師が解説
感染しても8割の人はうつさない!? 「新型コロナ」感染の特徴は?
